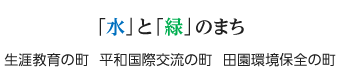公開日 2017年12月13日
更新日 2017年12月13日
南部茅の由来
岩手県には茅葺き材となる葦(ヨシ)の生産に適した土地が少なかったため、この地方で多く育つ山茅(ススキ)が茅葺き材として伝統的に利用されてきました。こうした茅の収穫は、村の共有地の茅場で各戸が行いましたが、茅場維持のための火入れなどは村総出で行っていました。
しかし、戦後になって村の相互扶助システムが消え、岩手県内でもまとまった茅場がほとんど見受けられなくなると、近場で茅が手に入らなくなってしまい、茅葺き屋根の維持が困難になるようになってきました。
そこで、「NPO法人 岩手で茅葺き技術の伝承を促進する委員会」により、岩手県内に新たな山茅の茅場をつくる計画が立てられ、金ケ崎町千貫石地区の遊休県有地において、山茅の企業的生産モデルの開発に着手しました。茅葺き棟梁や茅葺き企業の指導・協力を得ながら、様々な調査・研究・実験を行い、数年にわたる試行錯誤の末に茅葺き用山茅の企業的生産モデルが作り上げられました。
この結果を受けて、私たち「一般財団法人 金ケ崎町産業開発公社」(理事長:金ケ崎町長)はこのモデルを採用し、岩手県との協議の結果、無償使用を認められた千貫石地区の県有地約200ヘクタールを利用して、平成17年から山茅の企業的生産を開始しました。
このような背景のもとに生産された金ケ崎町の山茅(ススキ)の名称は、岩手県内唯一の集団的茅場産であることを象徴するものとして「南部茅(なんぶがや)」と命名されて県内外に流通しています。

南部茅の特徴・品質由来
ススキを使用しています
宮城県や青森県のような葦(ヨシ)の生産適地の乏しかった岩手県では、伝統的に茅葺素材としては、葦ではなく、生産の豊富な薄(ススキ)が使用されました。南部茅も、岩手伝統のススキを使用しています。
岩手地方の伝統的な収穫方式で生産された茅材です
当地においては伝統的に、晩秋に刈り取り作業を開始し、大雪の降る可能性の高い12月中旬ころまでに刈り取りを終えます。刈り取った茅は束ねて穂の方を上にした状態で、寄せ掛けて(「しま」立て)越冬させて、十分に乾燥した茅を春に収穫します。
この「しま」立てには大雪による倒伏を防ぐほか、降雪・強風により茅の乾燥を促進される効果もあります。これは雪の多い岩手で生み出された知恵・収穫方式であり、南部茅もこの方式で収穫されています。

葉つきが主流です
非降雪地帯の山茅(ススキ)が、茅場で越冬中に葉のほとんどを脱落させるのに対して、南部茅は晩秋に茅場で刈り取り、越冬中や春の収納作業中などに相当部分の葉がついたまま倉庫に収納されるのが普通であり、非降雪地帯の山茅に比べて茅束に葉がついたまま残っています。
岩手では伝統的にこの葉つき茅が屋根葺きに使われてきたので、葺き上がった屋根の印象はまろやかで柔らかい印象となります。
出荷茅の保管中の整形
倉庫に保管中の南部茅については、その姿がまっすぐに伸びるように積み替えなど保管方法の改良をはかっており、1年間の保管期間を通じて、多くの茅束の荷姿は相当程度までまっすぐに整形されています。
関連記事
- 金ケ崎町産かやぶき用茅材「南部茅」(2017年06月21日 金ケ崎町産業開発公社)